自作PC初心者がやりがちなパーツ選びの失敗例5選【2025年版】」
初めての自作PC。「パーツは適当に安いのを揃えればいいよね?」
その考え、マジで危険です。自作PCはパーツ選びがすべてを決めると言っても過言じゃない。
今回は、自作初心者が100%ハマる「パーツ選びの失敗パターン」をランキング形式で徹底的に解説します。実際の悲劇的なエピソードも追加したので、同じミスを繰り返さないようにしよう!
パーツの基本がまだよく分からない人は、【2025年最新】自作PCってなにが必要?全パーツ完全解説の記事を先にチェック!
この記事もおすすめ

🥇【ワースト1位】CPUとマザーボードのソケット互換性エラー
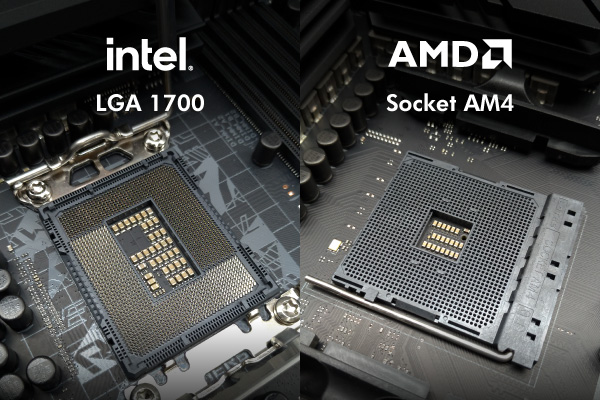
✅実際の悲劇エピソード
Aさん(20歳・大学生): 「AMDのRyzen 7を買って届くのを楽しみにしてたら、マザボがIntel用だった。組もうと思った瞬間、絶望した。結局、どっちかを売って買い直すハメに…」
【ソケット違いって何?】

CPUとマザーボードにはそれぞれ「ソケット(接続口)」があり、これが合わないと絶対に刺さらない。ソケットの互換性は自作PCの基本中の基本
- Intel系ソケット:LGA1700、LGA1200など
- AMD系ソケット:AM5、AM4など
【よくある勘違い】
- 「マザボの商品名に書いてあるIntelかAMDの2つに注意しておけばOK」→実は確認が不十分
- 「Ryzenならなんでも同じソケットじゃないの?」→世代によって違うので要注意
- 「高いCPUなら大体のマザボで動くだろう」→メーカーやシリーズが違えば非対応なことも・・・
【絶対回避する方法】
- CPUを先に決定し、必ず「型番+対応マザーボード」で検索
- マザボの商品ページで「対応CPU」欄を確認する習慣をつける
- 分からない場合は、PCパーツ検索サイトで互換性チェック
【ポイントまとめ】
- CPUとマザボの互換性問題は初心者の失敗トップ
- ソケット形状が物理的に異なるため、間違えると100%組み立て不可能
- 購入前に必ず互換性を複数の情報源で確認すること
🥈【ワースト2位】GPUサイズとケース互換性問題


✅実際の悲劇エピソード
Bさん(22歳・社会人): 「RTX4070を買ったら、ケースの横幅に収まらなかった…。結局ケースを買い直す羽目に。完成が1週間遅れて、休みが潰れた。」
【なぜ起こる?】
近年のGPU(グラフィックボード)は非常に大きくなっており、奥行き30cm超えも珍しくない。しかし初心者が選ぶ格安ケースは、小型GPUしか想定していないことも。特にハイエンドGPUは発熱対策で大型化しており、物理的なサイズを事前確認することが重要。
【グラボのサイズの調べ方】
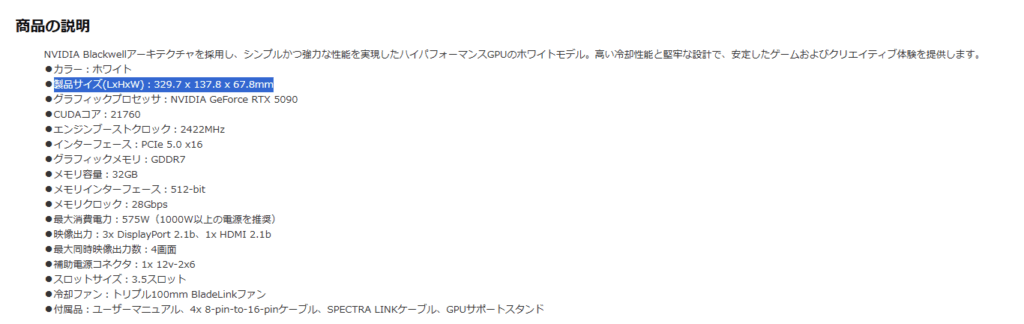
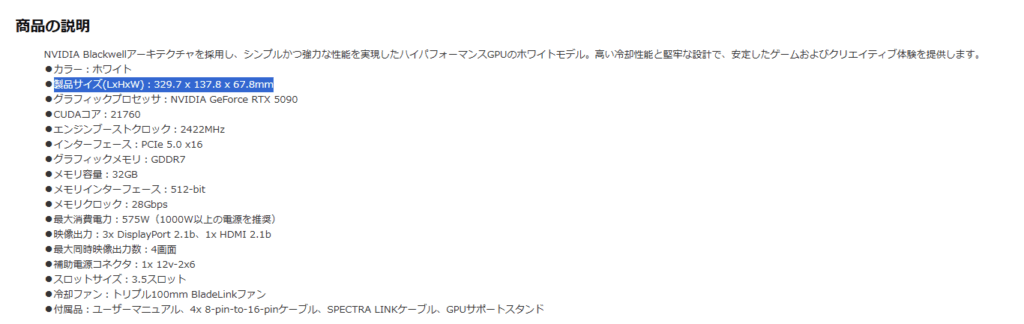
- Amazonや公式サイトの商品ページに必ずサイズ(mm)が記載されている
- 特に注意すべきは「奥行き(長さ)」「高さ」と「厚さ(スロット幅)」の3点
- RTX5080/4090クラスなど80番90番クラスなら3スロット以上の厚みも珍しくない



説明欄に書いてあります!!
【回避方法】
- ケースの商品ページで「GPU対応サイズ」を必ずチェック
- グラボより数cm余裕を持ったケースを選ぶ(特に奥行きは+2cm以上が望ましい)
- 無難にミドルタワーケースを選ぶのが初心者には安全
- 拡張性を考慮して、将来のアップグレードも想定したサイズ選び
【ポイントまとめ】
- GPUとケースのサイズ互換性は購入前の確認が必須
- 特に最新世代のグラフィックカードは大型化しているため注意
- ケース選びではコンパクトさより拡張性を優先しよう
🥉【ワースト3位】電源ユニット容量不足による故障リスク


✅実際の悲劇エピソード
Cさん(19歳・専門学校生): 「RTX3060用に450Wの格安電源を買ったら、起動数分で異音がしてPCが落ち、そのまま電源が死んだ。マザボも巻き添えで2万円が無駄に…。」
【電源ケチると何が起きる?】
電源ユニットは全パーツの命綱。安物やワット数不足は、最悪すべてのパーツを巻き込んで死亡する。特に負荷時の電力安定性が重要で、ゲーミングPCでは電源の質が全体の安定性を左右する。
【選び方の基本】
- GPUがRTX4060(5060)以上なら最低650W、RTX4070(5070)以上は750Wを推奨
- 「80PLUS認証」は効率と安定性の証。Bronze以上が安定
- 玄人志向、Antec、Corsair、SilverStoneなど定評あるブランドを選ぶ
- モジュラー型は配線がすっきりするが、非モジュラー型の方が安価
【初心者に推奨する電源スペック】
- RTX3060以下:500W~550W(Bronze以上)
- RTX4060~4070:650W~750W(Gold推奨)
- RTX4080以上:850W以上(Gold以上推奨)
- 予算に余裕があれば、将来の拡張性を考えて一ランク上のワット数を選ぶ
この商品は価格と性能のバランスが良くておすすめです!!
【ポイントまとめ】
- 電源は「守り」のパーツ。ここでコスパ重視は命取り
- ワット数と品質の両方を確認し、安定性を最優先
- 電源の故障は他パーツに波及するリスクがあることを認識
🚩【ワースト4位】メモリ規格互換性エラーによる起動不能
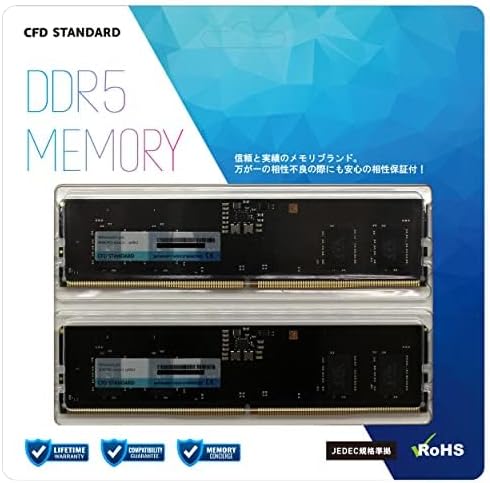
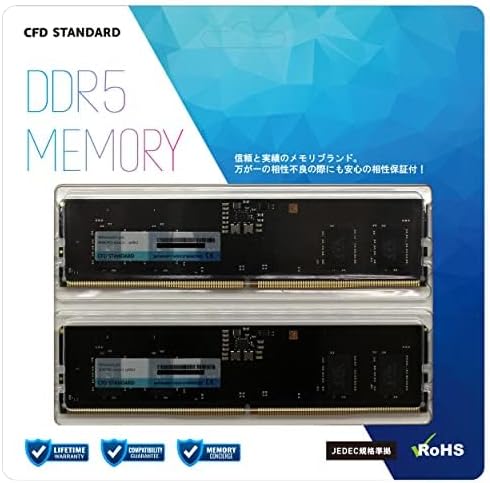
✅実際の悲劇エピソード
Dさん(21歳・フリーター): 「DDR5対応マザボを買ったのに、間違ってDDR4のメモリを買ってしまった。物理的に差し込めないので、すぐ気づいたけど無駄になった。」
【規格間違いとは?】
現在主流のメモリ規格はDDR4とDDR5の二種類あり、両者は互換性がない。マザーボードの対応規格に合わせないと動作しない。DDR5は高速だが価格も高く、DDR4とは物理的な形状も異なるため、間違えるとスロットに挿入すらできない。
【メモリ規格を確実に確認する方法】
- マザボの商品ページに対応規格が必ず書いてある
- Intel 12世代以降やAMD Ryzen 7000シリーズなら基本的にDDR5だけど、安いマザボならDDR4のことも多い
- DDR4/DDR5違いは商品名に明記されているので注意深く確認を
- メモリを挿す場所も決まっており、マザボ説明書に従う(デュアルチャネル時はA2・B2推奨)
【容量と速度の選び方】
- 16GB(8GB×2枚)が最低ライン。ゲーム用途なら32GBが理想
- 速度(MHz)も重要。DDR4なら3200MHz以上、DDR5なら4800MHz以上推奨
- 「安いから4GB×4枚」とかは絶対避けるべし。速度低下の原因に
- 同一メーカー・同一モデルの複数枚購入が安定性を高める
【ポイントまとめ】
- DDR4とDDR5は物理的に互換性なし。マザボ選びの時点で決定
- メモリはデュアルチャネル(2枚セット)で使うのが基本
- 容量と速度のバランスを考えた選択が重要



性能がいいCPUでコスパを求めると、DDR5のマザボにDDR4のメモリを買ってしまうミスが起きるかも!!
💥【ワースト5位】PCケース冷却性能不足による熱問題


✅実際の悲劇エピソード
Eさん(23歳・社会人): 「全面ガラスパネルのケースがかっこいいから買ったら、内部が熱暴走で動作不安定になった…。結局冷却ファンを追加購入。」
【見た目重視ケースの罠】
- ガラスケースや密閉系ケースは通気性が悪く熱がこもりやすい
- RGB満載の見栄えだけ重視したケースはエアフロー設計が不十分なことも
- 小型ケースは配線が地獄。初心者にはかなり難易度が高い
- 光モノ重視で機能性を無視すると後悔する
【初心者向けのケース選び】
- フロントパネルがメッシュ(通気性抜群)タイプを選ぶ
- 吸気・排気の経路が確保されたエアフロー重視設計を選択
- ケース付属の冷却ファンが多い(最低2〜3個)ものを選ぶ
- 内部レイアウトと配線スペースが広いモデルを選ぶ
- ケースレビューで必ず「配線のしやすさ」「冷却性能」を確認
- 拡張性を考慮して、ミドルタワー以上を選ぶのが無難
【冷却問題の症状と対策】
- PCが不安定になる、ゲーム中に突然シャットダウンする
- CPU/GPUの温度が90℃以上になる
- ファン音が異常に大きくなる
- 対策:追加冷却ファンの設置、ケース内ケーブル整理、CPUクーラーの換装
【ポイントまとめ】
- 冷却性能はPC安定性の要。見た目よりエアフローを優先
- 初心者はミドルタワー以上の作業スペースのあるケースを
- 将来のパーツ交換も考慮した選択が重要



恥ずかしながら、ゆきんこのメインPCはこのトラブル絶賛発生中・・・
ケースを買い替える記事出すかもしれません。
【番外編】初心者がよくやる自作PCパーツ選びの凡ミス


- CPUクーラー忘れ:CPUクーラーが別売りなのを知らず、熱暴走で起動不可に(一部CPUはリテールクーラー非同梱、同じCPUでも同梱してあるものと、してないものがある場合も)
- ストレージ容量ケチり:500GBのSSDしか買わず、ゲーム2本でディスク満杯に(近年のゲームは100GB超も珍しくない)
- Wi-Fi非対応マザボ:「無線LANは当然ついてる」と思い込み、結局追加購入(Wi-Fi内蔵は明記されているか確認。ちなみに、後からUSBに差し込むタイプも購入できる)
- SATAケーブル不足:マザボ付属のものだけでは足りず、別途購入する羽目に(追加のHDD/SSD用に予備を持っておく。基本的にはM.2で刺すのでSATAが足りなくなることはないかな??)
- OS購入忘れ:「Windowsって無料じゃないの?」と勘違いして予算オーバー(正規ライセンスは必須)
- マザボのサイズ間違い:MicroATXケースにATXマザボが入らない(規格サイズを必ず確認)
- グラボなしでディスプレイ接続:せっかくGPUを買ったのに内蔵グラフィックスに接続(グラボのポートに挿す)
- BIOS互換性問題:新CPUに対応していない古いBIOSバージョンのマザボ(アップデートが必要)
自作PC成功のための3つの黄金ルール
- パーツ選定は「CPU → マザボ → GPU → メモリ → 電源 → ストレージ → ケース」の順番で進める
- 「安すぎる」は罠。特に電源とケースはケチらない(ケースは見た目も大事だけどね笑)
- パーツ購入前に必ず対応規格・サイズ・互換性をチェックする(複数のサイト・レビューで確認)
これら3つのルールを守れば、失敗率は劇的に下がります。特に「互換性チェック」は最重要で、PC構成確認ツールを使うと安心です。
初心者が自作PCを失敗しないために
この記事で紹介した失敗は、誰でも簡単に回避可能なものばかり。パーツ選びの段階で「気づけるかどうか」がすべてを決めます。
ぜひこの記事を何度も見返して、自作PC初心者が陥りやすい悲劇を事前に回避してください!
「失敗しないパーツ選び」ができれば、自作PCの成功率は80%以上アップします。一度経験すれば、次からは簡単になるので、最初の一台を慎重に組み上げていきましょう!
次回予告:「Amazon?ドスパラ?どこでパーツを買うべきか」
次回は、自作PCパーツを買うのに最適なショップを徹底比較します。安さだけじゃなく、安全性や保証の面からもおすすめ店舗を紹介するので、お楽しみに!
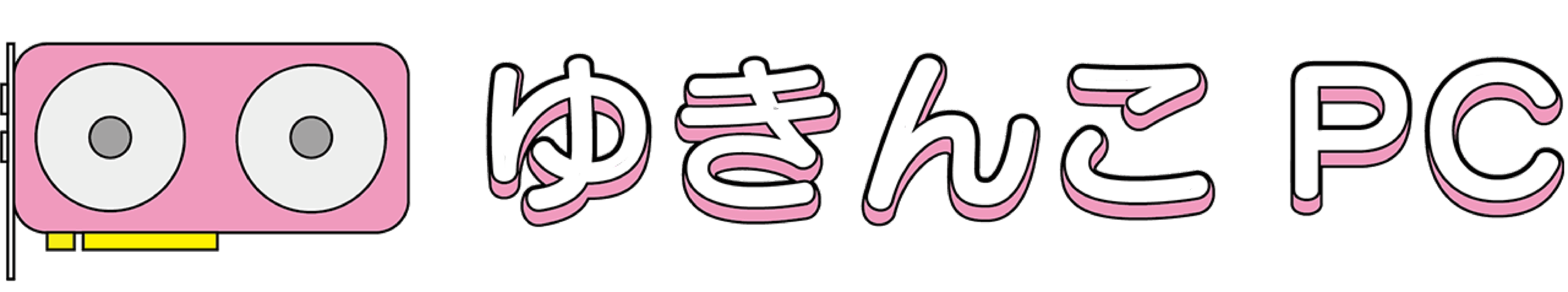


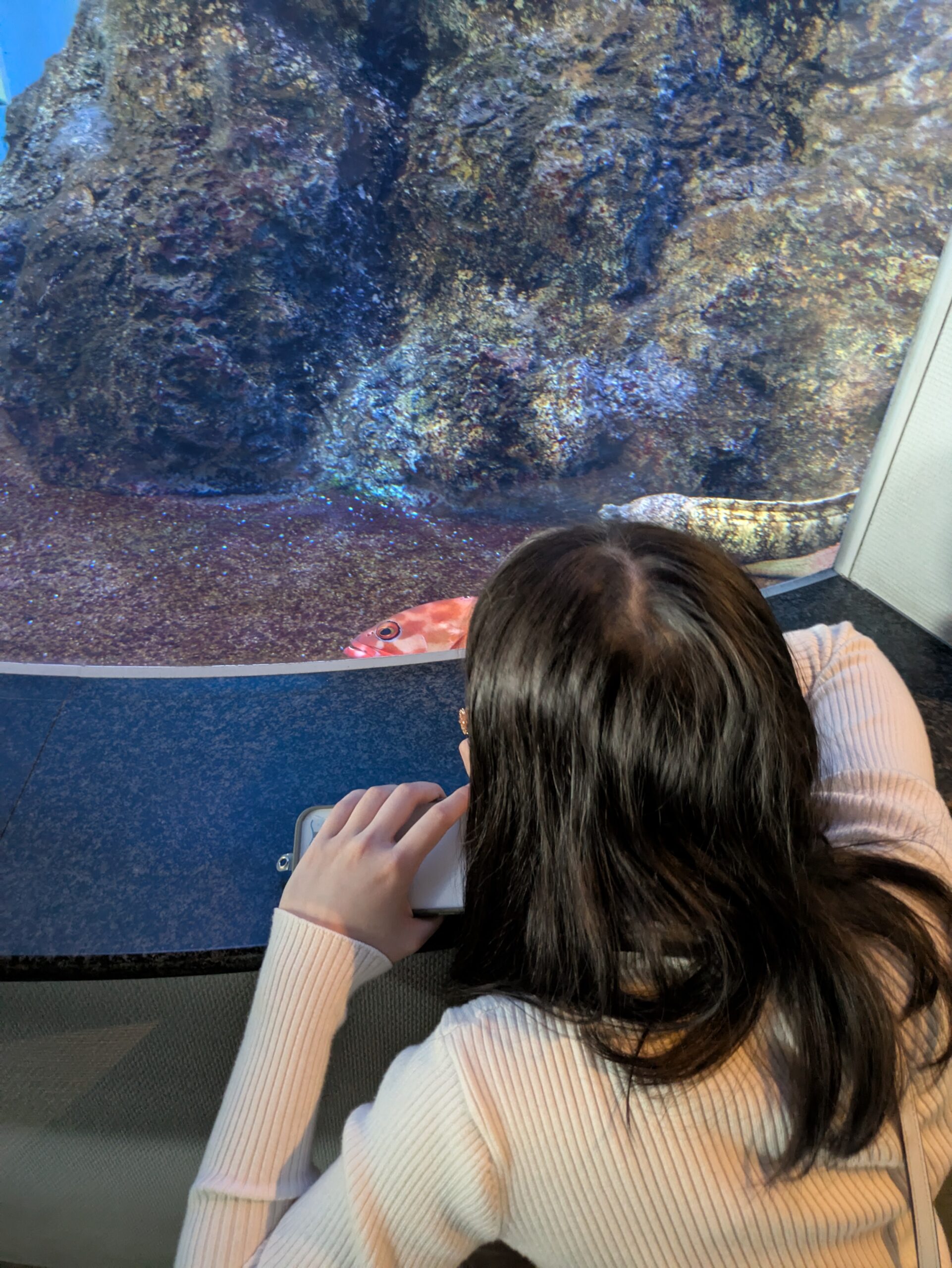

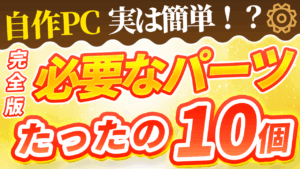

コメント